暗号資産は世界中で取り扱われていますが、各国でその規制は異なっています。
日本の取引所は登録制で、顧客保護の視点から預かり資産と事業資産の分離、ホットウォレットの上限などが定められています。
アメリカでは暗号資産が有価証券か商品かで議論が分かれ、中国では暗号資産から撤退し、エルサルバドルではビットコインが法定通貨になっています。
各国で暗号資産に関してのルールが変わり、マーケットが変わり、ユーザーにとっても使えるサービスが変わり、出来ることも変わります。
暗号資産をめぐる各国の規制を詳しく見ていきます。
暗号資産の各国の規制

日本
2017年の改正資金決済法
日本が国として「仮想通貨とは何か」という定義を定めた画期的な法律が、2017年に施行された改正資金決済法です。仮想通貨に対してここまで踏み込んだ法律をつくったのは、世界ではじめてのことでした。
仮想通貨を取り扱う事業者には、主に三つの義務が課されました。
一つ目は、仮想通貨交換業者(取引所)を登録性にしたこと。
二つ目は、マネーロンダリング(資金洗浄)を防ぐため、銀行と同じレベルで仮想通貨を取引する人の本人確認を徹底すること。
三つ目は、事業者が破産したときに利用者を守るため、顧客からの預かり資産と事業の運営資金を別々に管理すること。
2019年の資金決済法や金融商品取引法などの関連法令の改正
顧客から預かったコインの95%以上はコールドウォレットで管理し、ホットウォレットで管理する分と同額のコインを自社保有することや、それまで特に制限のなかった証拠金取引を金商法の規制対象とし、レバレッジ倍率の上限を2倍とすることなどがルール化されました。
また、この時から法令上の呼称が、それまでの「仮想通貨」から「暗号資産」に変更されました。
アメリカ
アメリカでは、暗号資産が株式などと同じ有価証券にあたるかどうか、長らく議論されてきました。
有価証券とみなされた場合、取り扱う取引所は登録が必要となりますが、そうでなければ運営の自由度は増します。
そして、アメリカの証券取引委員会(SEC)は、ビットコインとイーサリアムは有価証券ではないと明言しています。
一方、SECは、それ以外の暗号資産は証券である可能性が高く、SECへの登録が必要だと言及しています。
そして、SECのそうした動きとは別に、アメリカほ商品先物取引所委員会(CFTC)が、ビットコインを「コモディティ(商品)」と定めています。
ちなみに日本では「暗号資産は証券ではない」という位置付けです。
中国
当初、ビットコインの取引量でもマイニング事業者の数でも一大勢力を誇った中国ですが、徐々に暗号資産に対する締め付けが厳しくなってきました。
そして、2021年9月、中国人民銀行が国内での暗号資産関連事業の全面禁止を発表するに至りました。
中国は、ブロックチェーン技術を使った「デジタル人民元」の開発を強力に推進する一方、支配下にないビットコインに対しては断固とした態度をとってきており、ついに全面禁止 = 全面撤退となりました。
暗号資産における中国の影響力は、この先さらに縮小するものになると思われます。
エルサルバドル
暗号資産界隈でいま最も注目されているのは、中米の小国エルサルバドルの動向です。
エルサルバドルは、石油・石炭などの資源を持たず、九州の半分ほどの面積に650万の人々が暮らしていますが、経済的にも脆弱で、GDP(国内総生産)の2割をおもにアメリカへの出稼ぎ労働者からの仕送りに頼っています。
エルサルバドルの自国での通貨ですが、以前は「サルバドールコロン」が1892年から2001年まで使用されていましたが、それ以降は米ドルが法定通貨の役割を果たしてきました。
ただ、それ嫌ったエルサルバドルのブケレ大統領は、2021年9月7日から、ビットコインを米ドルと並ぶ法定通貨に格上げして、世界を驚かせました。
アメリカに出稼ぎに行った人たちからの仕送りは、毎回手数料がバカにならず、そもそも銀行口座を持っていない人が7割もいるエルサルバドルですから、ビットコインの手数料の安さと、ビットコインのウォレットで、それまでよりも安く安全に素早く送金ができるわけです。
ビットコインの今後はエルサルバドルの動きに注目

実態を持たないバーチャルな通貨を法定通貨にするというエルサルバドルの「実験」が注目を集めているのは、エルサルバドルと同じ問題を抱えている国が少なくないからです。
もしエルサルバドルの試みが成功したら、同じくビットコインを法定通貨と同じ扱いにする国が出てきても不思議ではありません。
そうなるとさらにビットコインの価値が増してきます。
私たちは、テクノロジーの発明や進化によって破壊的なイノベーションが発生し、世の中に非連続的な変化がもたらされる現場をまさに目撃しているのかもしれません。
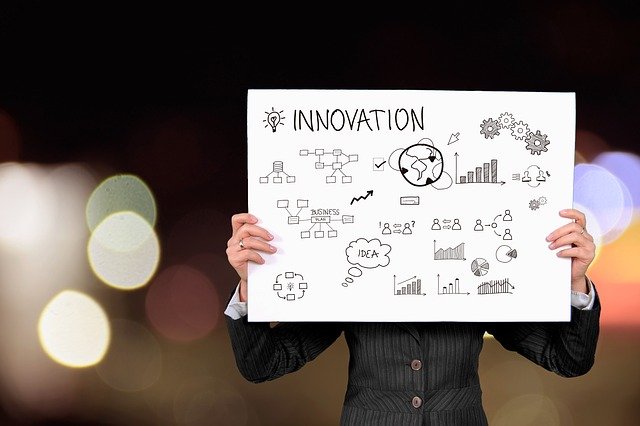


コメント